特別インタビュー
特別インタビュー
特別インタビュー vol.01

テレビ朝日映像(株)ディレクター 加藤 敦 氏
<略歴>
早稲田大学文学部演劇学科卒。記録映画、イベント映像、ドキュメンタリー番組などを中心に手掛け、代表作品として「オリエント急行がやって来た(フジテレビ)」「テレメンタリー 我が子の心臓手術(テレビ朝日)」などがある。現在BS朝日で放映中のパナソニックスペシャル「伊藤元重の経済×未来研究所」のディレクターを務めるなどテレビ番組制作の世界で活躍している。
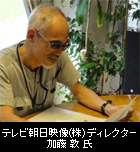 日本の製造メーカーに求められる競争力とは、
日本の製造メーカーに求められる競争力とは、価格でなく価値の勝負になる
●価格の安さでなく、日本独自の価値づくりが必要
日本の生産財メーカーは卓越した技術力を備えているにもかかわらず、縁の下の力持ち的存在に甘んじており、自ら積極的に広報活動に取り組んでいないせいもあって、テレビなどマスメディアに紹介される機会が少ないですね。
これから日本のメーカーが価格だけで競ってもアジアの企業には勝てなくなりますから、どのように独自の競争力を発揮していくかという視点が必要になりますね。
●ガラパゴス化する日本の技術開発には、ある面では大賛成
日本にしかない固有の伝統や四季それぞれの季節感に裏付けられて生まれてきたモノづくりを、日本のメーカーはこれからも大切にすべきだと思います。
携帯電話のように高機能化が進みすぎて、世界基準にならなかったことで、ガラパゴス化と冷ややかに言う人たちもいます。
しかし見方を変えると、製造業の分野では日本人だから生み出せる、どこにもない機能や価値をつくり出す力が存在するわけですから、この点は大いに誇りにしてもいいと思います。
●日本はアレンジャーとしての強みを発揮したい
日本人はゼロから1を生み出すことより、1を100にすることに何よりも長けていると思います。
未知の領域にチャレンジすることももちろん必要ですが、1ある資源を活用して100にする技術なり製品を生み出すアレンジャーとしての能力も生かして欲しいですね。
例えば電波天文衛星「はるか」の展開パラボラアンテナや、「きく8号」のアンテナに使用されるパネルですが、打ち上げた時にはたたまれていて、宇宙では開くという技術は、東京大学名誉教授の三浦公亮(こうりょう)先生が考え出された「ミウラ折り」と呼ばれる折り紙の技術が応用されています。
この発想はまさに日本人だから考えだすことができた画期的な技術だと思いますよ。
【編集部注釈】
東京大学名誉教授の三浦公亮(こうりょう)先生の折り紙のノウハウは、地図を折る技術として広く使用されている。
4個の平行四辺形の繰り返しで構成されている「二重波形可展面」という折り方に、British Origami Society(英国折紙協会)が「ミウラ折り」と名付け、世界的に知られている。
「キリンチューハイ氷結」の缶のパッケージにも「ミウラ折り」の発想が生かされている。
●業界の常識に囚われない発想とは、 リミッターをはずすことから始まる
医療機器メーカーのテルモ㈱が考え、岡野工業が実現した「痛くない注射針」などが好例ですが、これまでの常識や業界の固定観念にとらわれない柔軟なモノづくりの発想こそ、これからのメーカーには必要なのだと思います。
細いパイプをつくりそれを切って使うという従来の注射針発想でなく、材料を曲げるという発想でステンレスの深絞り加工を活用して、針の先端が蚊の口吻とほぼ同じ針を生み出したわけです。
前例に囚われることなく、新たな発想と既存技術の応用によって、画期的な商品を生み出すという日本人の強みがいかんなく発揮されています。
こうした斬新な発想視点に立つには、先ずつくり手の心にあるリミッターを外すことだと思います。
【編集部注釈】
リミッターとはクルマなどで速度に制限を与える機械のこと
●難題に直面すると、それを解決するアイデアを生み出すところが日本人の真骨頂
選択肢がたくさんあると見えてこないことが多いのですが、これしかないという状況になると、人は集中して考える力を発揮するようです。
自分たちの力を過小評価せず、やってみようと考えて行動を起こせば光明は差すのだと、これまで取材させていただいた方々から学びました。
大企業や取引先の下請けではない
●テレビや視聴者のイメージでは「縁の下の力持ち」
テレビの制作者や視聴者から見ると、生産財メーカーや部品メーカーのイメージは「縁の下の力持ち」であり、嫌な表現ですが下請けという印象を持つ人もいます。
しかし取材してみると、こうしたイメージを良い意味で裏切ってくれるメーカーが存在しています。
既存のイメージを裏切る取り組みが報道されることで、こうした企業の業界の「発見」なり「再認識」につながります。
視聴者がびっくりし、既存イメージを裏切る要素を備えている企業は強いと思います。
●大切なのは潜在ニーズを探るイマジネーション
「3ミリ径のドリルの歯を、メーカーから1000本を受注した」場合、多くの企業は受注して喜び、納品してそこで終わりです。しかしここで、イマジネーションを働かせる企業は、「スペアも含めて1000本必要ということだが、耐久性の高い製品を500本生み出して納品すれば喜んでもらえるんじゃないか?」
「3ミリの穴を開けるためには、もっといい道具があるんじゃないか?」といった発想に立ち、新たな提案をする企業も存在します。
取引先の求めることを見極め、課題を解決する提案を行い、相手の価値を大切にしてくれるメーカーなら、取引先は大事にしてくれます。
取引先メーカーと同じ土俵と目線に立ってビジネスをする。先方が気づいていないコストダウンの方法を提案する。こうした取り組みができる企業なら、下請けなどとは決して呼ばれないでしょう。
取引先の価値を高めるパートナーとしての地位を確立することが、何より求められているのだと思います。
単に量産化を重視してモノづくりの基準を下げてしまっては、マネされる製品になるだけですからね。
多面的にモノを見る目を備えている

●プロとは「段取りと準備」に時間をかける人
プロと呼ばれる人たちは、自身の持つ技術力はもちろんですが、仕事をどう進めるかという段取りと準備を周到にしているから、完成した製品の精度が高くなっている点を見逃すわけにはいきません。
量産品と違い、職人さんのつくるものは、世界にひとつしか存在しません。
この誇りが職人さんを支えているのだと思います。
力量のある職人さんほど、自分の技術を部下に教えています。
自分の仕事に自信と誇りがあるからです。
私たちテレビ制作の世界でも同様です
いいカメラマンとは、耳がいい。
いい音声さんとは、目配りがいい。
と言われます。
この意味は、良いカメラマンとは取材する相手の話をよく聞いていて、
相手が核心に触れる話を始めるとレンズをズームインさせていきます。
ところが絵作りばかり考えるカメラマンは、単に「絵になる」映像で終わってしまいます。
同様に音声を記録するスタッフも、カメラマンの映像表現を考えて、音声を収録するからよい作品に仕上がるわけです。
職人さんはともすると、ひとつのことだけに集中しがちですが、素晴らしい仕事をするプロとは、多面的に物事を見ている人だと思います。
●自分の可能性を広げるには、実際に自分がつくった製品を使って皮膚感を養うこと
職人さんに必要なこととして、自分が作ったものを自分でも実際に使ってみることが必要だと思います。実際に使ってみて初めて、「こんな便利なんだ」「こういう具合に役に立つんだ」ということが理解できるからです。
こうした皮膚感を持つ人こそ、プロの本領なのでしょうね。
耳の不自由な女性のドキュメンタリー番組を制作した時のことです。取材中にその女性が、女性にしては大ぶりな腕時計をつけていました。気になってその時計のことを尋ねると、振動式の目覚まし機能のついた腕時計でした。普通の時計と違い、目盛りが6分割で10分単位で目覚ましをセットできる機能を備えているのです。
私もこの時計が欲しくなりあちこち探した結果、手に入れ、今でも愛用しています。
自分で使ってみて初めて、こんな便利なんだという点と、主人公の気持ちが肌で理解できたひとつの例です。
●100年以上続く老舗企業が発揮する革新性と女性の活用にこそ、学ぶものがある
日本で100年以上続いている企業を調べてみると、意外なことにチャレンジ精神が旺盛で、革新的な技術を開発して今日に至っていることがわかりました。
保守的な考え方や変化に対応できなった企業は、残念ながら消滅しています。
老舗企業は第二次大戦など戦争を経験していますが、戦争で男手がいなくなると、いち早く女性が活躍できる場を提供したのが老舗企業で、法整備がされる前から男女の雇用機会は均等になっています。
老舗企業ほど女性の力を認め、女性の繊細さや発想などを研究しています。
これからの日本の企業を考える時、100年以上続く企業のあり方を老舗企業から学び、老舗企業の魅力と強さを再発見・再評価する意義はとても大きいと思います。
●企業の財産とは、やはり人
田中貴金属工業㈱という企業では、精錬技術のトップに身体障害者の方を採用し、定年後も教育リーダーとしていつまでも残っていてほしいと慰留して、現在も活躍されています。
その職人さんは金の不純物を取り除く際に、機械ではできない色や光から不純物の判別ができる方で、その力量を大切にしているわけです。
またこの企業では社員のお誕生日を社長がお祝いする誕生日会を催しています。
社員と現場の意見を大切にするひとつの取り組みです。
会社の財産とは人ですから、人のことをもっと知ろうというひとつの姿勢なのでしょう。
こうした取り組みをする企業には、報道する側としてはやはり惹かれますね。

